大学入試小論文対策の第一歩「高校生が知っておくべき小論文の基本とコツ」についての記事です。
今や一般入試、国公立2次試験はもちろん総合型選抜や学校型選抜でも小論文の攻略は欠かせないものになります。できることなら受験直前期に対策を講じるのではなく、高校2年生、いや、高校1年生の時点からしっかりと対策を行えば、確実に小論文で合格点を勝ち取れるものだと考えます。
高校生が知っておくべき小論文の基本とコツ

今回はその中でも小論文の書き方「超基礎編」をお伝えします。今更聞けないような超基本的な内容をお伝えしていきます。原稿用紙の使い方に加えて、句読点の使い方などなど、超基礎内容からお伝えします。
そもそも小論文とは?
まず、小論文は、作文でないことを理解しておかなければなりません。
- 作文…自分の感想を述べる
- 小論文…課題に対して、自分の立場(賛成・反対)を明示し、理由を述べる
一言で、言えば、上記の違いがあります。たとえば、「憲法改正」についての課題が出た場合、それについて、賛成か反対かを明記して、例示などを使って理由を述べていきます。
問題を提起と立場を明確に
課題によっては、自分の立場(賛成・反対)を明記しづらいものをときでも、第一段落で、自ら問題提起をすることで、その立場を明らかにすることができます。
小論文の流れ
- 問題提起をし、自分の立場(賛成・反対)を明記
- その理由
- 例示・展開(歴史的背景、第3者的な視点、原因など)
- 結論
以上ような流れで書くと、書きやすいし、採点する人とっても読みやすく好印象を与えることができます。結果、高得点を獲得できるというわけです。小論文を、効率よく、バランスよく書くコツは、いきなり書き始めるのではなく、メモを活用することです。さきほどのように、4段落構成にする場合、1000文字で内容を記述する場合、1段落200~300文字程度になります。
メモでは、段落毎に、外せない文言、最も言いたい文言を箇条書きに列挙していき、まずは、並べてみます。そこに、接続詞や言い換え表現、形容詞をさらに肉付けし、全体的なアウトライン(大枠)を決めます。そうすることで、書いている途中に、大幅に変更することもなく、スムーズに記述していくことができます。
小論文は、作文と違い、自分の立場を、はっきり明示することが大事です。その上で、「小論文の流れ」に沿って、記述していきます。要は、最初の問題提起です。これに関しては、日ごろからニュースや本を通して、自分は、それぞれ社会で起こっている出来事について、どんな問題意識を持っているか、「その都度考えてみる」「意見をまとめてみる」「身近な人と意見を交わしてみる」といったことが大事です。小論文も、1日して成りません。日ごろの生活で、どんな問題意識をもって生きてきたかを問われているのです。
小論文の書き方の基本
小論文を書く際の最大のポイントは「わかりやすさ」です。設問に対してシンプルにわかりやすくズバリと答えを書くことが最善ではないでしょうか。複雑な表現技法やテクニックは蛇足でしかありません。読み手のことを考えて書くようにしましょう。
その際に有効なのが、最初と最後に、あなたの主張や答えなどをしっかりと述べることです。最初に主張や答えを明示することで、この論文で何が言いたいのかが明確になります。また、その主張に基づいて内容を構成していけばよいので、推敲もシンプルになりスラスラと書くことができます。最後も印象を残すために主張を繰り返すようにしましょう。
小論文の練習は、できるなら早いうちから始めておきたいものです。早ければ早いほどいいと思います。小論文の権威に以前インタヴューしたことがありますが、「いい小論文を書くには、本気でそのテーマと向き合うことが大切で、何度も推敲を重ね苦しみながら生み出すのもである」という言葉が強く印象に残っています。
時間をかけて小論文の書き方をマスターして、どんなテーマが来てもすらすらと書けるように日頃から特訓しておきましょう。
良い主張・意見の立て方
小論文ではどのような主張・意見を書けばいいのでしょうか。それは「現代」という時代をしっかりと意識した意見を述べるということです。なぜなら、小論文が問う問題はすべて「現代」の社会問題を題材にしているからです。
これは大学がまさに現代を研究する学問の場であるからで、教育学部も法学部も医学部も工学部もすべて現代の問題点を解決するために研究を行っているのです。では、現代とはどのような時代なのでしょう。
現代という時代を一言でいうと「個人の尊厳を第一に守ろう」とする時代です。個人の尊厳とは、その人らしさと言い換えてもいいもので、一人一人の生き方や価値観と密接なものです。現代という時代は、そういうものを最大限尊重していこうという時代なのです。
もう一つの特徴は「共同体の利益も守ろう」とする時代だということです。たしかに、一人一人の生き方や価値観も大切ですが、社会のみんなの幸福も考えなければいけません。個人の生き方や価値観があまりにも好き勝手にのさばれば、多くの人が衝突し不幸になることは目に見えています。そうならないように、個人も幸福になるし、社会全体のみんなも幸福になるように、お互いが尊重し合いながら共同体の利益を考えていくのが現代という時代なのです。
もちろん、全ての問題をこの2つの考え方で論じることはできませんが、まずはここから考えるようにすると小論文の書き方も変わってくるのではないでしょうか。すごい意見も知識も必要ではありません。現代を意識した答案こそ求められているのです。
小論文は、はっきりって事前の準備で勝負が決まります。過去に出題された設問などをしっかりと分析し、これから学ぶであろう学問領域について日頃からアンテナを張り、日常生活を送るようにしましょう。意識して生活するのと、無意識で生活するのでは大きな差に広がってきます。
また、ニュースや新聞などで議論になっていることに対して、400字程度で自分の考えをまとめる訓練を毎週欠かさずに行うようにしてください。はっきり言って対策を講じた人とそうでない人の小論文はまるで違います
設問にはYESかNOで答える
大学入試の試験科目の中でも「小論文」を苦手にする生徒が多いような気がします。理由を聞いてみると、「何を書けばいいのかわからない」「最初の書き出しがわかならい」といった相談を受けることが多々あります。
小論文には、数学のように明快な解法がないので、どのように書いたらいいのかわからないといった趣旨になるのでしょうが、小論文にもちゃんとした解法があります。書き方のパターンというものがありますので、それに従って文章を構成すれば、合格点の小論文を書くことができます。
小論文を書く場合は、まず、与えられた設問や課題に対し「YESかNOで自分の意志を伝える」という原則があります。自分の意志をYESかNOで答えた後は、なぜYESなのか、なぜNOなのか、その理由を説明して採点者を納得させれば合格点の小論文が完成します。より説得力がある理由がかけると高い評価につながります。したがって、最初の書き出しはYESかNOで答えるだけであって、何のテクニックもありません。自分が思う方の回答をするだけで十分なのです。
もちろん、以後の説明の段落で説得しやすい方を選んだ方がいいのですが、自分が率直に思う方を書いた方が、オリジナル感あふれる小論文が完成します。
採点者は小論文で何を見ているのでしょうか。それは、表現力や一般常識的な教養を見ることはもちろんですが、一番重要視しているのがあなたの意見なのです。
意見というのは、その意見に対し正しいと考えるのか正しくないと考えるのか、こうすべきだと考えるのか、それは間違いだと考えるのか、つまり「YES」か「NO」で答え、あなたの意見を論理的に主張することになります。
小論文の書き方は「YES」か「NO」で答えることが原則であることは理解できたとしても、実際問題、YESかNOで答えにくい問題も多々見られます。例えば、「民主主義について述べよ」などの設問があったとします。この場合は一見、YESかNOで答えられないような問題に見えますが、これを無理やりにYES、NOの問題に自分で変えてしまうのです。
「民主主義は国家にとって最善の制度なのか」などと、変えてしまえばYESかNOで答えることが可能になります。それに続けて、その理由を説明していけばよいのです。ただし、注意したいのが、「民主主義について述べよ」という設問に対して「民主主義は国家にとって最善の制度なのか」という小論文をいきなり書き出すのは危険です。題意に沿っていないと判断されてしまう可能性があるからです。
そこで、書き出しに注意しましょう。まず、設問を理解していることをアピールし、その中でも、この問題は避けては通れないなどの構成にすると題意に反しない小論文が書けるはずです。「民主主義は、個人の意見を尊重する国家のあり方で、今日までに人類は大きな発展を遂げてきました。では、民主主義は人類にとって最善の制度なのであろうか…」などとすれば自然な流れになるのではないでしょうか。
論理的な展開と段落構造
段落構成はシンプルにすることがわかりやすい小論文を書くときのポイントです。お勧めは5段階の構成にすることです。
- 主張:自分の主張や答えを明示
- 理由:主張や答え根拠をしめす
- 具体例:字数や内容によってはなくてもいい場合も
- 反駁:他の意見に反対し論じる
- 主張:必ず1と一致させる
字数制限が短い場合、反駁が書けない場合があります。また、具体例もダラダラと書かないように注意してください。
説得力のある小論文
小論文は、シンプルに書くということを守ることが最大のポイントとなります。構成は、主張、根拠(理由)、結論の3点は外せません。その上で、説得力さらにゆるぎないものにするために、反対側の立場に立ったり、例示を示したりすることで、肉付けをしていくことになります。
1.主張
意見・主張は、できるだけシンプルな自分の主張を述べてください。くだくだ回りくどいのはいけません。主張は、一番最初。つまり、第一段落の出だしです。「~だから、~です。」ではなく、「~だ。~だからだ。」という具合です。もっとも大事な部分です。
2.根拠(理由・具体例・反駁)
主張の根拠を示します。主張の後に記述するということになります。普通は、論理展開と言われ、反対側の立場(一般論)、例示を示します。自分の意見とは反対の立場なのですからこの部分は不要なのではないかと思われがちですが、この部分もとても重要です。
これは、自分の主張ばかりを展開するのではなく、反対論も理解した上でそれでもなお 上でそれでもなお自分の意見の方が正当だということを客観的に証明していく方が説得力のある論理的な文章になるためです。
物事の2つの側面を理解し、論理的に考察した上で自分の意見を主張するということは試験官への大きなアピールになりますし、さらに、反対論を記述することで自分の意見が相対的に一層正当に見えるということにもなります。したがって、この反対論の記述はとても重要だといえます。
また例示や具体例、経験談を交えるとよりオリジナルな文章となります。
3.結論
以上の根拠、論理展開ををふまえた上で愛護に、自分の主張を記述します。
時間配分のポイント
- 開始10分
- 実際に記述する
- 終了10分
大きく3つの時間を区切って、構想、記述、確認ということをしていきます。
1.小論文開始10分が重要
小論文試験での合否を分けるのは試験開始後10分~15分です。この時間の間に、問題を読み、自分の思考を具現化(マップ化)していくことが大切です。
0分~15分
- (1)制限時間と文字数を確認する。
- (2)問題を見て、どの型の問題かを判断する。
- (3)解答用紙の余白に答案マップを作成する。
- (4)答案マップと原稿用紙のイメージを重ね合わせる。
2.書き始める前に
次に必要になるのが、構成ですね。どういった段落分けをして、段落ごとにキーセンテンスはないかを考察して、論文の柱を決めるといいでしょう。そして、書き始める(終了10分前まで)
この構成に費やす時間が、解答時間のおよそ4分の1程度です。解答時間が100分であれば、25分ですね。
3.小論文終了10分
- (1)漢字や句読点等、細かい日本語の修正・確認をする。
- (2)原稿用紙全体の整形をする。
以上のように、はじめにすべきことは多く、最も大事です。いきなり書き始めるのではなく、文章を理解し、何が問われているのかを吟味したうえで、自分の考えを具現化して、どう展開していくかを決めて、文章家していきましょう。
原稿用紙の使い方のポイント
小論文は中身が大切だということは重々承知していますが、やはり、形式もしっかりと見られるもの。しっかりした内容が書かれていても、原稿用紙の使い方さえ知らない答案は読んですらもらえないです。まずは、原稿用紙の使い方についておさらいしましょう。
- 書き出しは1マスあける
- 改行して書き出す際も1マスあける
- 原則1マス使って句読点「、」「。」
書き出しは必ず1マスあけるようにしましょう。冒頭から1マスあけていないと、小論文の中身すら読んでくれません。初っ端から「小論文の書き方知りません。」とアピールしているようなものです。
改行した際は、段落がわかれることを意味しますので、改行後に文章を書きだす際にも1マスあけるようにしましょう。
文章には、読みやすさを心がけて句読点を必ず入れるようにしてください。原則、1マスに句点「。」読点「、」を打ちますが、文章の最後の文字が行の最後に来た場合は、文字と一緒に句読点をマスの中に入れて、行の最初に句読点が来ないようにしてください。
かぎかっこの使い方
かぎかっこの使い方は大丈夫でしょうか。「」や『』などなりますが、どのように使い分けていますか?かぎかっこを使うケースはよくありますが、次のケースを覚えておけば大丈夫でしょう。
- 音楽や書物などの作品名は二重かぎかっこ『』でくくる
- 強調したいときは、その言葉をかぎかっこ「」でくくる。
- かぎかっこ「」の中にかぎかっこを入れる場合は二重かぎかっこ『』
- 他人の文章を引用する場合はかぎかっこ「」でくくる
- かぎかっこ「」の最後の句点は不要
まず、一つ目の音楽のタイトルや書物の作品名を記述する際は、二重かぎかっこ『』で作品名を囲むようにしましょう。
つぎに強調したいときですが、例えば、新大学入試のテストは「思考力・判断力・表現力」が問われる。などのように、文章中に強調したいことがある場合にもかぎかっこを使うようにしましょう。
かぎかっこ「」の中に「」を入れたい場合は、二重かぎかっこ『』で入れるようにしましょう。例えば、「新大学入試の傾向を聞いてみると『難しい』という回答が多かった」のようにします。
また、他人の文章などを引用するときもかぎかっこ「」で引用した部分を囲むようにしましょう。
最後に、かぎかっこ「」の文章の最後ですが、「~である。」のように最後に句点を打つ人がいますが、「」内の文章の最後は句点は不要です。「~である」で締めてください。
!や?は使わない
よく新聞や記事のタイトルで「!」や「?」を見かけますが、小論文では使わないようにしましょう。
- 「!」や「?」は使わない
- 流行語も使わない
- 「ケータイ」などの略語も使わない
冷静に相手を説得する小論文では不要の産物です。実際に新聞の記事の中身に目を通してもらうとわかりますが、タイトルでは「!」や「?」を多用していますが、記事の中では使っていません。
流行語も使わないようにしましょう。「神ってる」などの流行語は一時限りの言葉です。きちんとした日本語で表現することが小論文には必要ですので、流行語を使うと、回答者の品格を疑われます。
略語も使わないようにしましょう。「ファミレス」や「ケータイ」、「マクド」などの略語が並んだ小論文を読んでみると解りますが、非常に幼稚な印象を受けます。
「ら抜き」言葉に注意する
- 「見れる」ではなく「見られる」
- 「食べれる」ではなく「食べられる」
- 「出れる」ではなく「出られる」
- 話し言葉も使わない
小論文でよく見かける間違った表現の一つに「ら抜き」言葉があります。ついつい使ってしまいがちな表現として、「見れる」や「食べれる」、「出れる」という表現があります。正しくは「見られる」と「食べられる」、「出られる」になります。
最近では、世間にかなり浸透してきているようですが、年配の方にとってみては日本語の乱れと思われがちです。採点者がどんな人物かわかりませんので、「ら抜き」言葉ではなく、正しい表現を使いましょう。
話言葉にも注意してください。「でも」は「しかし」、「だって」は「したがって」、「いろんな」は「いろいろな」、「~してる」は「~している」。細かいですが、せっかくいいことを書いていても、論旨が幼稚に見られてしまいます。気を付けてください。
文体は「だ・である」で、1つの文章は短くする
- 「です・ます」調よりも「だ・である」を使う
- 目安は1つの文章で長くても60字以内
小論文の文体は「~だ」や「~である」を使いましょう。「です・ます」調で書くよりも説得力が増します。もちろん、文体は統一してください。「だ・である」で書くのなら、最後まで貫き通してください。文体がばらけると、その人の論理性が疑われてしまいます。
また、小学生の文章でよく見られる現象に、一文が長すぎるという現象があります。ダラダラと言いたいことを書いていくと、一文が100字を超えてしまう生徒もいます。小論文でも同じ傾向が見られます。
どうしても相手を説得したいので、説明の文章は長くなりがちですが、長くても1つの文章は60字以内で納めるように心がけてください。長くなればなるほど、言いたいことが伝わりにくくなります。句点で切って、接続詞でしっかりとつなげてください。
逆に短すぎる場合も、なかなか言いたいことを説明するのに苦労すると思います。どうやったら伝わりやすいかを考えながら日頃の練習を行うようにしましょう。
熟語のひらがなは避ける
- 熟語はひらがなで書かない
- 漢字で書けない場合は、他の表現を使う
小論文を書く場合、熟語を多用すると文章が引き締まって見えます。「その方法はたくさんあるが」などよりも「その方法は多岐に渡るが」などの方が、小論文が引き締まって見えます。
しかし、ここで注意したいのが、熟語のひらがな書きは避けるということです。どうしても漢字が思い出せず「考慮」を「考りょ」、「抵触」を「抵しょく」などと書いてしまうと、「コイツ漢字すら書けないのか」と思われてしまうことになりかねません。その熟語の漢字を書けないのなら、他の表現を使うようにしましょう。
感情的な表現は使わない
- 「くやしい」「悲しい」「楽しい」などの表現は使用しない
- 主観的な意見ではなく、客観的な意見を書く
小論文では「くやしい」や「楽しい」、「悲しい」などの感情的な表現は基本的に使いません。なぜなら、小論文は主観的な意見を述べるのではなく、客観的な意見を述べるものだからです。
一人称は「私」
- 自分の意見を述べる場合は「私」を使う
小論文で自分の意見を述べる際、一人称は「私」を使うようにしましょう。他にも「僕」や「俺」、「自分」などの表現がありますが、小論文では「私」です。品格を疑われますよ。
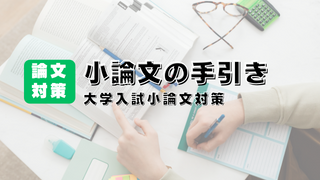
コメント